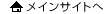リラックスして
福井 デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日は、午前中にお客様2件からの相談と連絡対応がありましたが、基本的に休みにしようと思いまして、ゆっくりとモデルルームで過ごしました。
日中福井は、気温34℃・湿度72%の様子で、外に出るとムッとした熱さでしたが、室内はすこぶる快適でした。
YouTubeで音楽を聴きながらソファーに寝そべって、リラックスしながら、頭を整理することができました。
テーブルの上に載っているのは、「カリモクケース」の新しいカタログと、「石巻工房」の新しいカタログです。
石巻工房の方のカタログは、中のデザインを息子が担当したというもので、置いていってもらいました。
こちらも、家の雰囲気に合えば、ぜひおすすめしたい家具になっています。
家を考える時、家具や調度品も大事だなポイントだなと、ますます思うところです。
名古屋にて②
福井 高性能住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日からお盆明けの仕事始めとなりました。
現場で、大工さん電気屋さんと打合せ。その他は、設計作業となりました。
さて、昨日の名古屋行のお話しです。
もう一つの目的は、セレクトショップの「cont」に行くことでした。
建物は、ほぼ倉庫という感じで、きっと倉庫をリノベーションして作られたのだろうなと思います。
中にある商品は、どれも洗練されたモノばかりで感心しました。
一部、月替わりで展示するギャラリーもあって、今月は「辻有希」さんのモビールの展示がされていました。
ショップの方も、当然かもしれませんが、作家さんに詳しくて、それぞれ特徴を説明してくださります。
福井の「ataW」さんと同じくらいレベルが高いなと思いましたら、お店の方もataWさんよく知っていらして、商品も展示されていました。ほかにも「SAVA!STORE」にも店員としていらしたことがあるとか、福井で開催される「RENEW」のイベントもお手伝いされるとか。
デザインの業界というのは、どこかしらつながっていて、情報を共有していらっしゃるものなのだなと思いました。
名古屋くらいだと、こういうセレクトショップがいっぱいありそうで、実は無いのだそうです。
次男のおかげで、質の良い店をこれまでも見てこられて、ほんと良かったなと思います。
お店の質って本当に大事です。
家もそうですね。どこで建てても同じではありませんからね。
名古屋にて①
福井 工務店 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日までお盆休みということで、次男と妻と、名古屋まで行ってきました。
目的は二つあったのですが、一つ目は栄4丁目の中日ビル1階にある、「ブルーボトルコーヒー・名古屋栄」でした。
こちらは、息子が春から務めている、「芦沢啓治建築設計事務所」のデザインによるもので、息子の勧めもあって見に行ってきたものです。
入るときから、ちゃんと席を案内し確保してくれて、それから注文に行きます。
注文も、決して慌てさせることなく、ゆっくり説明して選ばせてくれるので、ものすごく感じ良かったです。
お店は、空間がゆったりととられていて、抜け感もありながら、きちんとゾーン分けも出来ていて、ゆっくりとくつろげる感じでした。
壁のタイルと、それを照らす間接照明もとてもきれいでしたし、ペンダントやブラケットも芦沢事務所でデザインしたものが使われていて、その他は、目立たないグレアレスの小さなダウンライトが必要最小限付いているだけで、これは夜も見たいなとすごく思いました。
こちら、人を写すとよくないと思って、写真は控えてましたが、ちょっとお客様の空いた時に急ぎ撮ったものです。
今回、当社のモデルルームでも使っている、「カリモクケース」の家具も見たかったのですが、同じ空間に、ナチュラルな「ピュアオーク」とダークな「スモークドオーク」の家具を同時に使っているのを見て、すごく感心しました。
それが、きちんとゾーン分けされて置かれているので、まったく違和感が無いのです。
建築とインテリアと照明が、見事に調和して出来ていて、とても居心地の良い空間になっています。
トータルでやっている建築事務所さんだからこそ出来るのかなと思いました。
本当に、良い勉強となりました。
もう一つの目的は、明日ご紹介したいと思います。