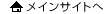春の陽気と上手につきあう、家の空気の話
昨日に続き、気温も19℃ほどで外の空気が気持ちいい一日でした。自宅も事務所もモデルルームも、今日はエアコンを切って窓を開け、掃除をしながら春の空気を感じていました。そんな日にこそ、換気の基本を思い出したいと思います。
(施工事例-Roftより)
1)気候の良い日は「窓」を上手に使う
FPの家は、断熱・気密がしっかりしているので、季節がちょうど良い時期はエアコンに頼らなくても快適に過ごせます。窓を開けて風を通しながら掃除をすると、気分もすっきりしますよね。こういう日は、自然の風から空気を取り入れて過ごしていただくのも、とても良いと思います。
2)窓を開けても「換気システム」は止めないほうが安心
ただ、窓を開けると家の“気密”(すき間が少ない状態)が保てなくなり、計画した通りに家の隅々まで換気が行き届かなくなります。窓から窓へショートサーキットを起こすからですね。だからといって換気システムを止めてしまうと、今度点けるのを忘れてしまうこともあります。窓を開ける日でも、換気システムは基本「入れっぱなし」にしておくのが無難です。
3)これからの季節は、窓より「フィルター換気」が頼りになる
春先は花粉やPM2.5、黄砂が気になる時期に入ってきます。そうなると、窓を開けて気持ちよく…というより、窓は閉めて換気システムに頼るほうが安心です。当社の第3種換気は、汚れた空気(湿気やニオイも)をシンプルに排出する考え方で、給気口(レジスター)側で花粉対策やPM2.5対応フィルターも選べます。家の空気を汚さず、新鮮な空気を取り込み続けることが、結果的に住む方の健康を守る土台になると思います。
窓を開けたくなる陽気は嬉しい反面、空気の流れは意外と見えにくいものです。だからこそ「気持ちよく開ける日」と「閉めて守る日」を使い分けつつ、換気は止めずに上手に付き合っていきたいですね。
見学会やモデルルームでは、空気の感じ方(におい・湿気・温度ムラ)も含めて体感できます。ご予約やご質問は、公式LINEからお気軽にメッセージください。
FPの家の省エネを支える「蓄熱」の話
越前市での完成見学会(3/7・3/8)に向けて、今日は左官工事の残りが終わり、エアコンの取付も行いました。玄関まわりもきれいに納まり、いよいよ「暮らしの空気感」を体感いただける段階です。今回は、FPの家の省エネを支える要素「蓄熱」について書いてみます。
1)玄関が整うと、家の“表情”が出てきます
玄関ドアが納まると、建物の顔つきが一気に引き締まります。
外壁の質感や庇(ひさし)の影の出方も、仕上げが進むほど素直に見えてきますね。
今日は左官工事の残工事も完了し、外まわりの印象がより完成形に近づきました。
こういう節目の日は、家づくりの積み重ねが形になっていくのを感じます。
2)24時間全館冷暖房を“省エネ”にする鍵は「蓄熱」
FPの家は、24時間の全館冷暖房を基本にしていますが、無理なく続けるには「蓄熱」がとても大事です。
エアコンで室内を暖めはじめると、空気だけでなく床・壁・天井も少しずつ同じ温度に近づいていきます。
家がゆっくり温まり、ゆっくり冷める状態ができると、温度の波が小さくなり、体感がやわらかくなります。
結果として、エアコンの風だけに頼らずに済み、省エネにもつながっていきます。
3)FPパネルのつくりが、熱を逃がしにくい理由
少しだけ仕組みのお話をすると、FPパネル(ウレタン断熱材)は柱いっぱいに納まり、余計な空気のすき間をつくりにくい構造です。
そこに空気層を設けず、石膏ボード(室内側の下地材)を直に納めることで、熱が壁の中へ抜けにくく、室内側にとどまりやすくなります。
その結果、石膏ボード自体に熱が溜まり、輻射熱(ふくしゃねつ/体を包むように伝わる熱)がじんわり出てきます。
「風は強くないのに、なんだか暖かい」——そんな感覚の背景には、この蓄熱の働きがあります。
完成見学会は、写真では伝わりにくい“空気のやわらかさ”まで確かめていただける機会です。玄関まわりの納まりや質感とあわせて、蓄熱による心地よさも、ぜひ現地で体感してみてください。
完成見学会(3/7・3/8)は【予約制】です。公式LINEのチャットに「見学希望」と送ってください。空いている時間をご案内いたします。
出窓を“スクエアに見せる”ロールスクリーンの納まり
越前市の完成見学会のお宅、ダイニングの出窓をご紹介します。出窓は飾り棚としても使える反面、ロールスクリーンの「機械部分」が見えると窓が重たく見えがちです。今回は、上げた時にすっと消える納まりを狙いました。
1)出窓は“見せ場”だから、サッシ際が大事
出窓は、季節の小物を置いたり、光を楽しんだりできる場所です。
だからこそロールスクリーンは、できるだけサッシ面に近い位置がきれいだと感じます。
生地が手前に下がってくると、出窓に飾ったものや置いてある小物がスクリーンに隠れてしまい、せっかくの“使える棚”が生きにくくなります。
今回の窓は特にスクエアが綺麗なので、その輪郭を崩さないことを最初に決めました。
2)上げた時に“メカが見えない”と、窓が軽くなる
ロールスクリーンは、上げた時に巻物やメカが視界に入ると、窓の印象が一気に変わります。
そこで、庇(ひさし)の中にスクリーンが納まるための「凹み」をつくり、見え方を整えました。
納まりとは、部材どうしの収まり方のことですが、こういう小さな差が居心地に効きます。
結果として、スクリーンを上げている時でも窓がスッキリ見えるようになりました。
3)薄い庇のまま成立させるために“横付け”で考える
ただ、出窓の屋根を大きくすると外観のバランスが崩れやすいので、庇はなるべく薄くしたい。
その条件の中で、縦寸法が大きくなりがちなスクリーンをどう隠すかが悩みどころでした。
そこで取付方法を工夫して、横方向に取り付ける納まりを検討しました。
取付業者さんも初めてのケースだったようですが、設計の意図を理解してくれて取付。狙い通りに隠れてくれました。
設計と現場がきちんと噛み合うと、窓まわりの“静けさ”が出てくるなと改めて感じます。
窓は大きさや形だけでなく、「使い方」と「見え方」の両方で完成します。小さな納まりの工夫が、毎日の気持ちよさにつながる。見学会でもぜひ実物で確認してみてください。
完成見学会のご予約・ご質問は、公式LINEからお気軽にどうぞ。空き枠のご案内もLINEでスムーズです。