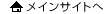時間も手間もかけて
福井 高気密高断熱 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日は、午前中にお客様宅メンテナンス相談と現場確認。その他は経理と設計作業でした。
昨日、足場ばらし前の2階以上のサッシクリーニングをお願いしたので、確認してきました。
足場ばらしが土曜日になっていて、それも前倒しできないか依頼しましたが、こちらはダメでした。早く外したいところですが。
内部は、大工さんに細かい造り物をいろいろとお願いしているのですが、コツコツ作ってくれております。
こちらは、トイレの埋込の収納スペースです。扉も後から付ける予定です。
壁にボードを張るだけなら、きっともう工事も完了しているかもしれないのですが、当社の場合、手の込んだことをいろいろとやっていくので、時間も手間もかかります。
でも、出来ると良いものになりますからね。
ISHINOMAKI ELEPHANT KIT
福井 住宅設計 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日は、急ぎの発注作業をあれこれ行ってから、施工図と設計作業を行いました。
途中、現場の寸法確認に行きましたが、日中はまだ厳しい暑さです。
さて、こちらは「石巻工房」の象の工作キットになります。
好きなように紙やすりで磨いて、角を丸めてもいいということのようで、キットには紙やすりも付いてくるのですが、このままが好きですね。
首だけが磁石で動くようになっています。
デザイナーさんは「トラフ建築設計事務所」ということでした。
シンプルにデザインされていて気持ちがいいです。
私も住宅以外に、家具の設計とか、こういう備品のデザインもしてみたいです。
MOHEIM
福井 住宅設計 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日は、朝のうちに外構工事現場打合せと和田中の現場確認と打合せ。その他は、発注作業とあれこれ頼まれごとの手配と、メインの設計作業を行いました。
月曜日は、雑用が多くなるのですが、なんとか予定の作業まで進みました。
さてこちらは、名古屋のブルーボトルコーヒーで手に入れてきたマグカップです。
外側が、マットな素焼きのようになっているのですが、内側は釉薬がかかっていて、実用を考えたものです。
こちらは、特に素焼きっぽい色のカップですが、ブルーボトルコーヒーのマークが入っております。
カップの底には、メーカーの印刷があるのですが、「MOHEIM」ですね。
なんと福井の会社さんの製品でした。
とてもデザインの優れた生活用品を作っている会社さんです。
そういえば、ゴミ箱もモデルルームで使っておりました。
福井も、優れた会社さんありますし、もっと県や市も宣伝・応援すべきだと思いますね。